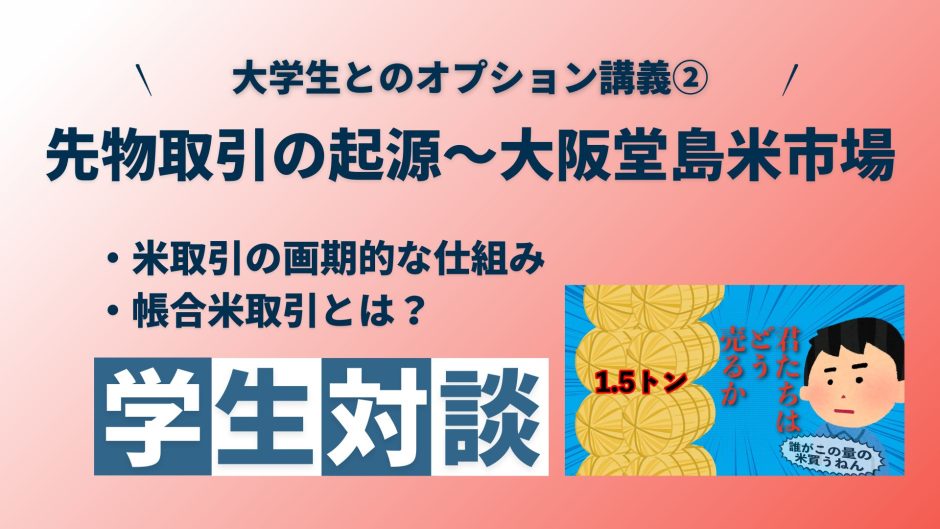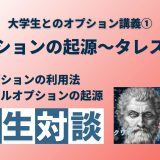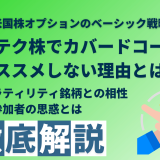※このコンテンツは大学生でもわかるコンセプトとして教育目的で話しており学生にオプション取引を進めるものではありません。

こんにちは、オプショントレード普及協会の守屋です。
こんにちは、オプショントレード普及協会の金森です。
今回も投資に関してはほとんど知識のない大学生であるうどんくんとオプション取引について学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

よろしくお願いします!

今回は先物取引の起源である、大阪堂島米市場の話を守屋先生にしていただこうと思います。
守屋先生よろしくお願いします。

目次 閉じる
先物取引の起源「大阪堂島米市場」

はい、前回はオプション取引、特にコールオプションの起源としてタレスについて話しましたが、今回は先物の起源「大阪堂島米市場」について話していきたいなと思っています。
うどんくんは先物取引についてどんなイメージがあります?
そうですね、まぁやっぱり正直なところ難しいっていうイメージですね。
あと、何をしているのかわからないという印象で、初めて「先物取引」と聞いた時に、
「先に物を取引するのか、それで?」という感じでしたね。


まぁ確かにうどんくんと同じように考える人は多いかもしれないね。
先物は難しい、怖い、あるいは金融工学が生み出した意味のわからない物、なんて思う人は実際多いのではないかと思います。
でもね、元々は米の値下がりのリスクを回避するために自然に生まれたテクニックみたいなもので、みんなが思っているほど難しくて恐ろしいものではないですよ。
そうなんですね。
昨日は先物というものすごい強敵と格闘する想像をして、眠りにつきましたね。


そう考えるか(笑)。
でも実際先物がどのようにして生まれたのかとか、本当に強敵なのか、今日の話を聞きながら考えてもらいたいなと思います。
ということで早速本題に入っていきたいと思いますが、今回の堂島米市場の話の舞台は江戸時代の大阪です。
当時は経済においてお米が中心的な役割を果たしていたというのは有名な話だよね。
当時はお米が税として納められていて、それを大阪に集めて〜みたいなことは聞いたことがありますね。

米切手による取引

そうだね、堂島の米市場はその中心地であったわけなんだけれども、よく考えてみると、そのお米を納めるといっても、大量のお米をやり取りするのは大変ですよね。
当時はどうやって運ぶんだろうね。
まぁ現物で取引するのは流石に不便だと当時の人たちも気づいていたんでしょうね。
そこで米切手の登場です。これは紙です。
今で言う有価証券、お米券みたいな感じかな?
それを使って、お米券をお米の代わりに相手に渡していたと言うことなんですよ。
確かに、紙になったのならば、現物よりか遥かに軽くて便利ですよね。


そうだね、当時の文献には、紙になったので火事になった時でも、その紙を持って逃げることができるだとか、あるいはネズミに食べられる心配もなくなったということが書かれているくらい、紙にすることで便利になった可能性があります。
で、紙にすると言うことは、結局米切手というものが実は金融の道具になっていったということなんですよ。
金融の道具というのは、例えばお米が自分の領土から上がってくる前に、先にお米券を発行して、そのお米券でお金を融通するということができたわけです。
ということはその米切手は市場に流通するわけで、それを手にした人は、米切手の価格変動がリスクになるわけです。
そうですね。


下がったらどうすればいいのか、というと、普通だったら値下がりしそうになったら米切手を手放せばいいですよね。
そうですね。


ところが、お米券と言っても10キロ程度のお米券ではなく15トンです。
だからそのお米券を売りたくても、みんなそう簡単に買えるかな?買う人いるかな?
いや、すごい量のお米を取引できるほどみんながみんなお金持ちではないですからね。
まとまったお金を用意するのは時間がいることですよね。


そもそも15トンにもなるお米券で15トン分のお米をもらっても仕方がないよね。
それを買うお金もすごく高いだろうしね。
だから買い手が少ない。
売りたくても売れない。
さっきうどんくんが言ってくれた通り取引の参加者が少ない、サイズも大きすぎる。
ということで、この状態を手狭と言ったんですね。
流動性がない状態。
ということは、やっぱり取引の参加者を多くする、あるいは米切手の値下がりを防ぐ方法を何か考える必要がある。
そこで考えたのは取引の参加者を多くすればいいのではないかということだったんですね。
では、多くの参加者を獲得するにはどんなことが必要だと思いますか、うどんくん?
商品を持っていなくても売れる先物の登場
えーと、月並みなことしか言えないんですけどやっぱり敷居を低くすることじゃないですかね?


そうだね、その通り!
じゃあ敷居を低くするってどういうことかなって考えてみると、まず商品の売買だから、買う人は物を持っていない人だよね。
じゃあ物を持っていないと売れない、とすると物を持っている人が少なければ売れないでしょ?
そうですね。


なので、考え方としては参加者にフラットに参加してもらうために物を持ってなくても売れる、当然物を持ってない人は買えるんだけどね、物を持っていない人でも売れる状態を作ったんですよ。
そうすれば、物を持っている人しか売れない状態では物を持っている人しか参加できないけれど、物がなくても売れるんだったら誰でも参加できるよね。
確かにそうですね。


だから、物を持っていなくても「売れる」という仕組みを考えてお米券の下落リスクをヘッジできるようにしたのです。
物を持ってなくても売れるということは、逆にお金を持ってなくてもその時買えるんですよ。
この仕組みだと、売る約束と買う約束を今しているだけだから、今お金がなくても、今物がなくてもやれるよね、という仕組みなんです。
じゃあ、今約束するときにお金がなくても実際に売買するまでにお金を用意すればいいということになりますので、お米を買う人の敷居が結構下がりますよね。


でも結局最後には米の売買をするんだったら、どうせその時点でお金要りませんか?
そして大量のお米が必要じゃない?
うーん、確かにそうですね。

実際のお米の売買にならない仕組み

そこで、大阪の堂島は実際のお米の売買にならなくてもいいようにしたんですよ。

本来、約束したのであれば、実際に約束の期日には物を買わなければいけない、売らなければいけないということなんだけれども、実は大阪の米市場では約束の期日までに、買う約束をした人は必ず売る約束を、売る約束をした人は必ず買う約束を別にしてください、というルールにしたんですよ。
うーん、なるほど。


そうすると、買う約束をした人が売る約束をしたら、それで互いに相殺をする。
そして、売る約束をした人が買う約束をしたらそれも相殺する。
結局物のやり取りをしなくてもいいということになったわけだ。
じゃあ、お米も、お米を買うのに必要なお金も持ってなくていいということになりそうですね。


そうなんですよ。
結局、買いますと言った約束の価格と売りますって言った約束の価格の差だけをやり取りするようになったんですね。
その差額だけをやり取りすれば良くなったので、その差額だけを用意すれば良くなったんですね。
それなら確かに、敷居がすごい低いですよね。
差額分を極論用意すれば大丈夫ということですね。


そうなんですよ。
ただ、その差額分ですら用意できない人がいたらこの制度は成り立たないですよね。
なので、当時からその差額分くらいのお金を用意して担保として差し出すルールがあったんだって。
これは今で言うところの証拠金っていうんだけどね。
まぁ、いずれにしても買う約束をした値段と売る約束をした値段があって、みんなのそれぞれの値段を調べて、この人はいくらプラス、この人はいくらマイナスっていうのを計算していた人たちがいたということだね。
当時すでにそのように清算する機関があったそうですよ。
それはすごいですね。
コンピュータや計算機が何もない時代に、要は全て手計算ってことですよね(笑)。


そうなんですよ、それでほとんどミスもなかったというからスゴいよね!
すごいですね。


で、こういうふうになれば、値下がりすると思ったときに自分の米切手を売るんじゃなくて、自分の米切手を持っておきながら市場ではとりあえず売る約束をするわけだ。
そして値下がりしたところで買う約束をする。
例えば、1,000円で売る約束をした後、値下がりして100円になったところで100円で買う約束をすれば、1,000円で売る約束と100円で買う約束が相殺されて清算機関から900円もらえることになります。
つまり900円儲かるということ。
自分の米切手は値下がりしていて損をしているけど、この約束取引(先物取引のこと)の儲けでその損失をカバーできるということなのです。
そうですね。


そんなふうにして、米切手の値下がりを違うところでカバーする、そんなやり方ができるようになったんですね。
今の話を聞いていると、すごく取引への参加のハードルが下がったように感じました。
やっぱり、徹頭徹尾多くの人に参加してもらうための制度だっていうことですね。


そうなんですよ。
これまで話してきた約束取引は今で言う先物取引のことだけれども、先物取引の「先」は「未来」という意味だね。
つまり、今やり取りするんじゃなくて将来にやり取りするっていう取引にすれば、今物を持ってなくても売れるし、満額お金を持ってなくても買う約束ができるような仕組みを作れるわけだよね。
このように将来に取引をする約束をするという仕組みを作ったわけだけれども、これは先ほど言った通り、物がなくても売れるということは、売る物はなんだっていいんですね。
架空の物でも良いわけだ。
しかし、実際は自分の米切手の値段が下がるのが嫌だからこういう制度を作ったわけなのだから、やっぱりお米の値段の取引をした方が良くないですか?
代表米を使った「帳合米取引」
まぁ、そうですよね、それは流石に…。


となると、お米が例えば九州のお米とか北陸のお米とかというふうにいろんな種類のお米があると、せっかく流動性を高めたのにバラバラだと市場にとって良くないよね。
そうですね、例えば「このお米が欲しい」という人が偏ってしまったら、そのお米しか取引されなくなってしまう可能性もありますよね。


そうですね、日経平均というのもそうだけどやっぱり何か一つの指数にした方がいいんですよね。
代表にね。
これ面白いのはね、堂島でも「代表米」っていうのを作ったんだよね。
日経平均みたいにお米も個別銘柄じゃなくて「代表米」にしたんだって。
一個に決めてしまうということですか?


そうだね。みんなが一個のものを見て、その一つにみんな集中して取引するようになれば、流動性が高まると思いませんか?
まぁ、そうですよね、取引がしやすくなりますよね。


ということでね、さっき言ってくれた通り一貫して参加者を増やす、そういう取り組みなんだよね。
確実に取引できる流動性があれば参加する気にもなりますよね。
繰り返しになりますけど、やはり取引に参加しやすくするための制度なんですね。


そうですね。
まぁ、今回「代表米」という日経平均のような一つの指数を使って取引を行う、ということ。
そして、当時始めからもうお米のやり取りをするつもりがない、始めから差金決済、売る約束と買う約束の価格の差だけでやり取りをしていたということ。
そしてこれは帳簿上での数字を合わせた取引ということで当時、帳合米取引なんて呼ばれていたんですよ。
じゃあ、帳簿上でお金の取引は済ましてしまっていたということなんですね。


そうなんですね。世界の商品先物は最終的には物のやり取りに進むのに対して、大阪堂島米市場ではお米の先物取引なのに実はお米の取引をしない、始めからそういうふうになっていなかったわけで、その意味では現代の指数先物取引(日経225先物取引等)は大阪堂島米市場で行われていた先物取引のほうが似ているんです。
そうなんですね。

帳合米取引の事例
それでは次に帳合米取引をこの場で模倣して実際にどのように取引が行われていたのかを考えてみましょう。
ではまず、米切手を持っている人の立場に立って、米切手の値下がりの損失をカバーするための帳合米取引の使い方を考えてみましょう。


そうですね。
実際に米切手の値下がりからの損失を防ぐために帳合米取引を使ったという話をしてきましたが、実際米切手を持っている人は米が値下がりするとわかった場合はさっさと売ってしまえばいいんですよ。
でも、話した通りサイズが大きすぎて売れないことやそれによって売る相手がいない「手狭」な状態だったんですね。
なので、米切手を売らないで帳合米を売ることにするんですね。
とりあえず、帳合米を今の価格で売る約束をするんですよね?


そうです。
そもそもこの帳合米取引は日経平均のような代表米という指数を取引する形にしたんだけれども、もともと「持っていない物でも売れる」ということに意味があるんですよね。
ということはうどんくんが言ってくれたように物がなくても売るという約束ができるわけだ。
ここでは代表米の値段を取引するんだけれども、実際代表米自体は取引できないよね。
そうですね。


現代風に数字を置き換えた方がわかりやすいと思うので、今回は、例えば1キロ1,000円くらいのお米があるとしようか、なので代表米という実際には手元にない物を1,000円で売る約束をするわけだ。
で、そのあと値下がりして500円まで下がったところで、実際に売る約束をしているので本当に売るとすると、1,000円で売る約束をしてるから、市場で500円で買ってきて1,000円で売りつければいいんだよね。そうするとこの場合500円の利益になりますよね。
そうですね。


そう、つまり値下がりする場合は先に売る約束をして後で安く仕入れればその分儲かるわけですよ。
ただ、今の事例では実際にお米の売買にまで進んでいますよね。
そうですね。

お米の売買をしないシステム

そこで堂島が面白いのはこのような実際の売買をしなくて良くしたんですね。
500円に値下がりしたときに500円で実際に仕入れるのではなく、
「代わりに500円で買う約束を入れるようにしなさい」
としたところなんですよ。
そうすると記録上では、1,000円で売る約束をした記録と500円で買う約束をした記録がそれぞれ帳簿に残って、その差額の500円だけをやり取りするというルールにしたわけなんですね。
なるほど、結局お金のやりとりをするのは500円を市場側からもらえるということですか?


その通り。
ということは今回は売りの約束から入った人の例だったけど今度は、買いの約束から入った人はどうなるかな。
えっと、買いの約束をした人は逆に値上がりしないと利益にならないんですけど、期日までには売りの約束をいれる必要があるので、500円に値下がりしたときに泣く泣く安く売る約束をしたとして、1,000円で買って500円で売るので、市場に500円支払う必要がありますね。
結局先に売った人が受け取る500円は先に買った人が支払う500円とも考えられますね。


そうなんですよ、まぁこれがよく言うゼロサムゲームと言うことですね。
では代表米の価格が上昇した場合はどうなるでしょうか。

制度上満期までに逆の取引をしないといけないので、代表米が1,000円か1,500円に上がったとすると、先に1,000円で売る約束を入れた人は、1,500円で買う約束をしなければならないので500円を市場に支払う必要があります。


そうですね。
ただ、この人が持っている米切手もこの場合は価格が上がっているよね?
ということは帳合米取引では損をしてしまったけれども、自分の米切手の価格が500円以上上がっていれば、全体的に自分の資産は減っていないと見ることができると思いませんか?
なるほど。

まとめ

だから先ほどの代表米の値段が下がった事例では自分の米切手の値段も下がっているわけですよ。
でも、帳合米で儲かった分を見れば全体としては資産は減っていないととれるわけです。
なので、代表米の価格が上がったときには先に売らなければよかったと後悔するかもしれないけれど、自分の米切手も値上がりすることを考えれば、資産は減っていないと考えられる。
代表米の価格が上がっても下がっても自分の資産を守ることができる、そんなふうに自分達の資産を守るためにこの先物取引という制度は作られたんだね。